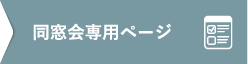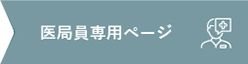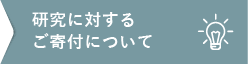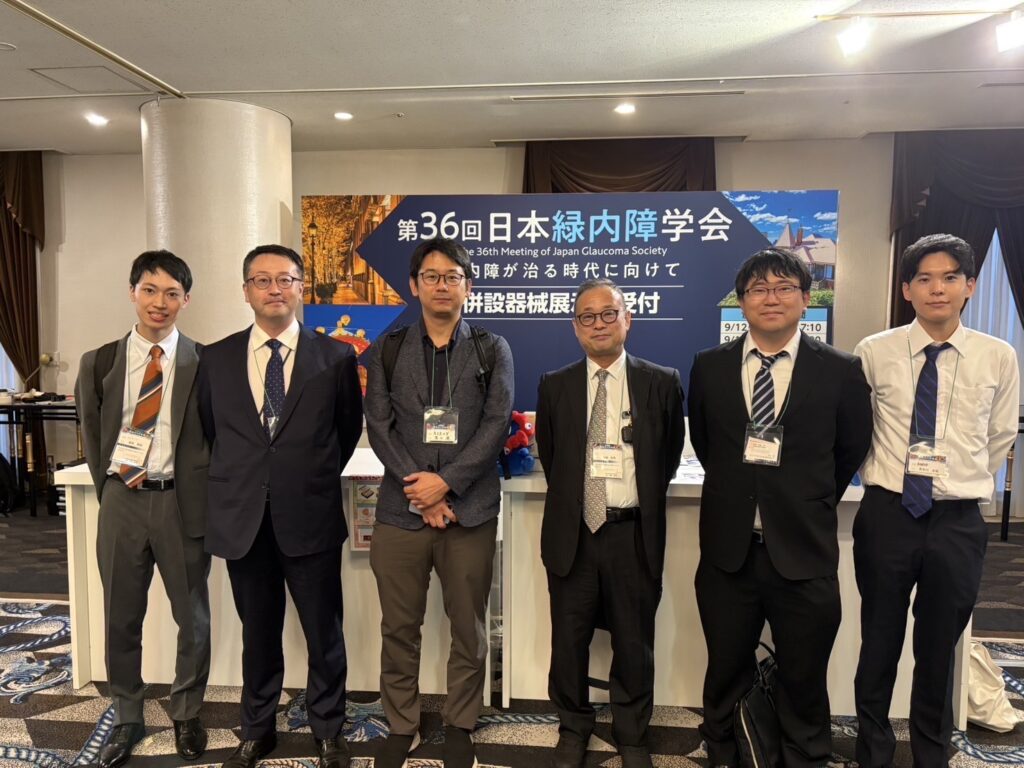はじめまして、10月のレジデント便りを担当します令和7年度入局の齋藤翠と申します。
日に日に日が短くなっていく今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
日常の業務には慣れてきましたが、初心を忘れず努力していきたいと考えています。
さて、先日北海道大学で開催された眼腫瘍学会に参加してまいりました。
研修医時代に他科の学会などいくつか参加してきましたが、そのどれとも比べ物にならないくらい活気がありました。毎演題後の質疑応答では議論が白熱しており、圧倒されました。眼腫瘍という生命にかかわる分野で、機能面・整容面などを考慮しながら手術をすることの難しさを改めて考えさせられました。
写真は学会の前日に眼形成分野の先生方とご飯をご一緒させていただいたときのものです。
初対面の先生もいらっしゃいましたが、とても明るく楽しく、眼形成分野の魅力について夜を徹して語ってくださいました。またとない勉強の機会をいただきました。
大学には多様な専門分野のプロフェッショナルの先生がいらっしゃいます。その方々のご指導のもとでこれからもしっかり学んでいこうと思っています。